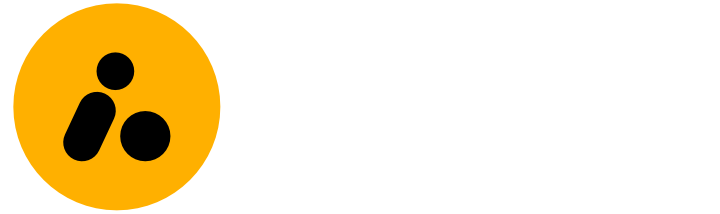校正に最も適したAIはどれ?同じ記事をAI校正で比較してみた

AIを使えば、ブログやWebサイトの文章を簡単に校正してくれるんじゃないか。
そう思って同じ記事を5つのAIに校正させ、比較してみました。
5つのAIツールに同一の記事を校正させた結果、Manusが最も優秀と評価されました。一方、他のAIは誤字や表現の指摘が不十分で、改善提案も雑で期待外れでした。AIは表現の統一、誤字・脱字の修正、構造的な整理の提案が弱く、信頼性の高い校正には人間のチェックが欠かせません。
結論から言えば、Manus以外のAIは期待ハズレでした。
結果的にManusの宣伝記事みたいになってしまいましたが、Manusからは何も受け取っていません(念のため)。
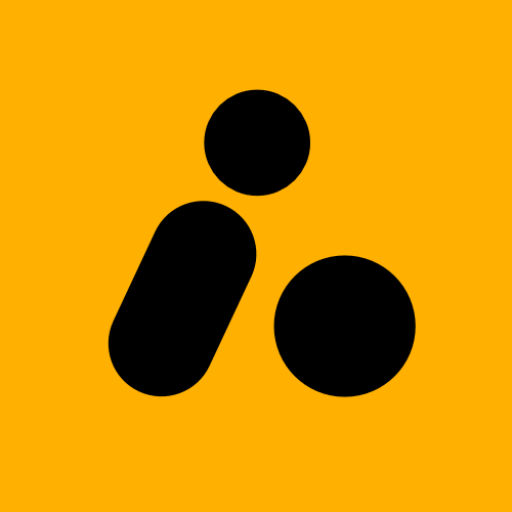
AI校正以外は、すべて手書きです。
今回はランキング形式でお届けしますが、記事執筆時点のものであることをお断りしておきます。
校正の対象にしたのは、下の記事です。

この記事は、校正前の状態を見て頂けるよう、修正せずに記事執筆時のままにしてあります。
プロンプトはこちら。全てのAIに同じものを投げています。ちなみに、このプロンプト内にも「変は言い方」という誤字を入れてみました。
次の記事を読んで、誤字や変は言い方があれば教えて。また、間違いではないが、もっとこうすれば良くなるという点があれば指摘して。
第1位 Manus
全体的にとても良く校正できていました。分量もちょうどいいです。
冒頭部分に(これから詳細に確認していく)という不明な箇所が出たのと、プロンプトに誤字がある点をスルーした点を除けば、満足のいく結果でした。
Manusは中国製なんですが、日本語の微妙な表現の違いなどもよく把握できていると思います。
結論がイマイチ明確でない点や、専門用語の解説などが指摘されているのも高評価でした。
校正全文(PDF形式)を、下からダウンロードして頂けます(別タブで開きます)。
発見した問題点・改善点
誤字・脱字・不自然な表現
(これから詳細に確認していく)
改善提案
(これから詳細に確認していく)
発見した問題点・改善点
1. 誤字・脱字・不自然な表現
重大な問題
- 「それ程高くはないとされていること」 → 「それほど高くはないとされていること」
- 「それ程」は「それほど」と平仮名で書くのが一般的
- 「推定と断った上で、下ような回答を出してきました」 → 「推定と断った上で、下のような回答を出してきました」
- 「下ような」は「下のような」の誤字
- 「なお、ChatGPTは別のサービスの推定クリック率も勝手に出してくれました(※Bing ChatはCopilotの旧名です)」
- この文は問題ありませんが、表現がやや口語的
軽微な問題
- 「どれくらいクリックされてるんだろう?」
- 「されてる」は「されている」とした方が丁寧
- 「私自身、出典リンクをクリックすることはあまり無かったので、そう思ったのかもしれません。」
- 「無かった」は「なかった」と平仮名で書くのが一般的
2. 改善提案(内容・構成面)
文章の流れ・構成
- 導入部分の改善
- 現在:「AIの回答画面(チャット画面)を見た人が、果たして出典リンクをクリックするだろうか、と思ったことはないでしょうか。」
- 提案:もう少し具体的な状況設定があると読者の関心を引きやすい
- データの信頼性について
- AIに聞いた結果と実際の調査データを明確に区別する必要がある
- 「ChatGPTによると」「実際の調査では」などの区別を明確にする
- 表の見やすさ
- サービス比較表は良いが、データソースの明記があるとより信頼性が高まる
専門用語の説明
- CTR(Click-Through Rate)
- 初出時に略語の説明があるが、記事全体を通してもう少し丁寧な説明があると良い
- SERPs
- 略語の説明はあるが、一般読者にはもう少し詳しい説明があると親切
文体の統一
- 敬語の使い方
- 全体的に丁寧語で統一されているが、一部口語的な表現が混在している
- 「〜してくれました」「〜出してくれました」などの表現を統一する
- 数字の表記
- パーセンテージの表記が統一されている(良い点)
- 数字の全角・半角も統一されている(良い点)
3. 内容面での改善提案
情報の整理
- 情報源の明確化
- AIからの回答と実際の調査データの区別をより明確にする
- 各データの出典を明記する
- 結論の強化
- 記事の最後に、調査結果から得られる示唆をまとめる
- AIO対策への具体的なアドバイスがあるとより価値が高まる
読みやすさの向上
- 段落の構成
- 一部の段落が長いため、適切に分割すると読みやすくなる
- 見出しの工夫
- 現在の見出しは適切だが、より具体的な数値を含めると興味を引きやすい
- 例:「ChatGPT:出典リンクのクリック率は5~15%」
4. 全体的な評価
良い点
- 調査内容が具体的で実用的
- 複数のAIサービスを比較している点が良い
- 海外の調査データも含めて包括的
- 表やデータの整理が適切
改善の余地がある点
- 誤字脱字の修正が必要
- 情報源の信頼性についてより明確な説明が必要
- 文体の統一をより徹底する
- 結論部分の強化
第2位 Claude
日本語能力に定評のあるClaude。しかし、今回の校正では全く期待以下でした。
引用記事のタイトルについて
- GEOではなくAEO(Answer Engine Optimization)が正しいと思われます
とありますが(7行目)、ここではGEOが正解。「AIなのに、AIのことが分からないのかな」と思ってしまいました。
もちろん正しい指摘もいくつもあるのですが、全体的に「古いタイプの校正者」の印象でした。
記事を読ませていただきました。AIの出典リンクのクリック率について詳しく調査されている興味深い内容ですね。以下、誤字や改善点をお伝えします。
誤字・不自然な表現
- 「AIO・LLMO・GEOの違いは?」 → 「AIO・LLMO・AEOの違いは?」
- GEOではなくAEO(Answer Engine Optimization)が正しいと思われます
- 「実際にクリックされていますか?どれくらいの割合の人がクリックしているか教えて。」
- 日本語として少し不自然。「実際にクリックされているのでしょうか?どれくらいの割合でクリックされているか教えてください。」の方が自然
- 「それ程高くはない」 → 「それほど高くはない」
- 「それほど」が適切
- 「うでない場合でもオーガニック検索からの流入は減っており」
- 「使っていない場合でも」の方が適切
より良くするための改善点
1. 構成・流れ
- 記事全体が少し冗長に感じられます。特に各AIへの質問と回答の部分は、もう少し簡潔にまとめられると読みやすくなります
- 海外サイトのデータの方が具体的で有用なので、そちらをより前面に出した構成も考えられます
2. データの整理
- 複数の調査結果が混在していて、数値の比較が難しくなっています。主要な数値を表やグラフでまとめると分かりやすくなります
3. 表現の統一
- 「クリック率」と「CTR」の表記が混在しています。どちらかに統一するか、初出時に説明を入れると良いでしょう
- 「AI要約」「AI Overviews」「AIオーバービュー」などの表記も統一した方が良いです
4. 引用の明確化
- 海外サイトからの引用部分で、どこからどこまでが引用なのか分かりにくい箇所があります。引用符や色分けなどで明確にすると良いでしょう
5. 結論部分の強化
- 最後の「AIOの主戦場はChatGPT」という見出しと内容が少しずれています。調査結果を踏まえた具体的な対策や今後の展望をより詳しく述べると価値の高い記事になります
全体的に非常に労力をかけて調査された貴重な内容だと思います。データの整理と表現の統一を行えば、さらに読みやすく価値の高い記事になるでしょう。
第3位 ChatGPT
いきなり
本文中には目立つ誤字や明らかなタイプミスは見られません。
とあり、全く機能していないことが分かります(5行目)。
自分は仕事ができないくせに、本質でないことを「あーだこーだ」と言い立てる、出来の悪い先輩みたいでした。
以下、記事「AIの出典リンクのクリック率(CTR)はどれくらい?AI時代のクリック率を徹底調査」(2025年6月26日掲載)についての校正・改善提案です。
✅ 誤字・誤用の指摘
- 本文中には目立つ誤字や明らかなタイプミスは見られません。ただし、「AIO対策」等の固有名詞表記に一貫性があるかは念のため確認をおすすめします(例:「AIO対策」「AIO・LLMO」など)。
- 日本語の文脈として、「ChatGPT/Geminiからの流入が増えたブランド」の節などで、英語の固有名詞と括弧書きの日本語訳が混在しており、一部読みづらい印象があるかもしれません。
📝 表現・構成面の改善提案
1. 見出し・段落構成の見直し
- 長い見出しや段落が多数あるため、読者が全体の流れをつかみづらいかもしれません。例えば、
- 各AI(ChatGPT/Gemini/Claude/Perplexity)の「クリック率」「傾向」「原因」の項目を表形式で整理すると、比較しやすくなります。
- 海外調査結果のまとめを、「全体傾向」「ブランド検索との違い」のように分類して見やすく整理するのも効果的です。
2. 定量データの強調と視覚化
- 海外の調査では「クリック率が‑34.5%」「平均‑40%」「中央値‑37%」といった数値が出ていますが、文章だけでは読み飛ばされやすいです。
- 箇条書きや表、太字で強調すると読者の注意を引きやすくなります。
- 可能ならグラフ(棒グラフ・円グラフなど)で視覚化するとさらに効果的です。
3. 用語や指標の補足説明
- CTR(Click Through Rate)は一度は説明していますが、記事後半で再登場するときに再度注記すると親切です。
- 「ブランドキーワード」「非ブランドキーワード」といった語も背景説明(どのように定義されているか)を明記するとより読み手にわかりやすいでしょう。
4. 結論・示唆を強化
- 最終的な提言部分(「AIOの主戦場はChatGPT」「ブランドがある場合はAIO掲載を狙う」など)は良いですが、読者が具体的にどのようなアクションを取るべきか、もっと明確に書くと実用的です。
- 例:「まずどのクエリでAIOが出現しているか分析する」「自社コンテンツをAIO参照されやすい構造に整備する(FAQ形式やリスト形式で)」「ブランド系クエリでの露出を強化する」など。
5. 引用ソースや信頼性の明示
- ChatGPTやClaudeなどAIに聞いたデータはAI自身の推定値という形で紹介されていますが、情報の信頼性に関して「推定・非公開データ」などである旨を明示すると、記事全体の信頼性が高まります。
✨ 改善ポイントまとめ
| 改善点 | 内容 |
|---|---|
| 見出し構成の整理 | 見出しを簡潔にし、比較しやすく構成を明確化 |
| 定量データの視覚化 | 数値を表や箇条で整理、可能ならグラフ化 |
| 用語の注釈追加 | CTR、ブランド/非ブランドキーワードなどの補足説明 |
| アクション提言の強化 | 読者が取るべき具体的な改善ステップの提示 |
| 出典・信頼性の注記 | AIの回答データは推定値である旨を明記 |
🔍 総評
内容としては非常にタイムリーで、AI時代の重要なCTR変化を具体的データで説明しており、読み応えのある記事です。ただ、「構造的に整理されていればもっと読みやすく、実務にも使いやすくなる」余地があります。
すでにかなりの品質ですが、記事をSEOやUX両面でさらに強化したい場合、上記の視点をご検討いただければと思います。
ご希望があれば、具体的に段落分けの案や見出し案などもお手伝いできますので、お知らせください!
圏外1 Copilot
どうもURL(https://aiotaisaku.com/aio/aictr/)にあるaictrという文字に引きづられているようで、全く無関係な「AI活用能力認定試験」の話を始めてしまいました。
プロンプト内の誤字を指摘できたのは評価できますが、それ以外は全くダメ。内容も短いし、評価以前の結果でした。
そのリンク先の記事「AICTR(AI活用能力認定試験)」について、内容を確認しました。誤字や不自然な表現は少ないですが、より読みやすく、信頼性を高めるために改善できそうなポイントをいくつか挙げますね。
📝 誤字・不自然な表現の指摘
- 「変は言い方」→「変な言い方」
※これはユーザーのメッセージ内の表現ですが、念のため指摘しておきます。 - 記事内には明確な誤字は見当たりませんでした。ただし、以下のような表現は少し曖昧です:
- 「AI活用能力を測る試験」
→「AI活用能力を客観的に評価する試験」など、目的がより明確になる表現にすると良いかもしれません。
✨ 改善提案(より良くするためのポイント)
- 見出しの強調が弱い
→「試験概要」「対象者」「試験のメリット」など、セクションごとに見出しを設けると、読み手が情報を整理しやすくなります。 - 箇条書きの活用
→試験の特徴やメリットを列挙する部分は、文章で続けるよりも箇条書きにした方が視認性が高まります。 - 「AI人材の育成が急務」などの背景説明があると説得力が増す
→なぜこの試験が必要なのか、社会的背景や企業ニーズなどを簡潔に補足すると、読者の納得感が高まります。 - 試験内容の具体例があると親切
→「AI活用能力」とは何を指すのか、例えば「データ分析」「AIツールの選定」「業務への導入判断」など、具体的なスキル例があるとイメージしやすくなります。
もし記事の執筆者であれば、読み手の視点で「この情報で安心して受験できるか?」を意識すると、さらに信頼性のあるコンテンツになりますよ。必要なら、文章のリライトもお手伝いできます!
圏外2 Gemini
Copilotの上をいくダメっぷりだったのがGemini。
一見、まともな内容に見えますが、読んでみると、存在しない文章を間違いだと指摘したり、使ってない用語を勝手に持ち出したりとムチャクチャな内容。
本当にこれがGemini⁈と驚くような内容でした。
実は、当初は「Geminiが一番すごいんじゃないか」と勝手に期待していただけにショックでした。
レビュー依頼ありがとうございます。AIO対策に関する非常に興味深い記事ですね。全体的によくまとまっており、分かりやすいと感じました。
以下に、ご指摘のあった誤字、変な言い回し、そしてより良くするための提案をまとめました。
全体的な印象と所感
- テーマが明確: AIOとAICTRという新しい概念について、SEOとの比較を交えながら分かりやすく解説しようとしている点が良いです。
- 構成が分かりやすい: 各セクションが明確に区切られており、読者が情報を追うのに苦労しません。
- 具体例が豊富: 各種検索エンジンのAI機能への言及や、具体的な対策方法が提示されており、理解を助けます。
誤字・変な言い回し(修正提案)
特に目立つものはありませんでしたが、より自然な表現にするための提案です。
- 「AICTRとは何か?」の見出し下の導入部分
- 現状: 「AICTRとは、AIを用いたコンテンツをターゲットとして、クリック率を最大化するための施策や戦略を指します。」
- 修正案: 「AICTRとは、AIが生成・利用するコンテンツをターゲットに、クリック率を最大化するための施策や戦略を指します。」
- 理由: 「AIを用いたコンテンツをターゲットとして」よりも「AIが生成・利用するコンテンツをターゲットに」の方が、AIの役割が明確になります。
- 「AICTRの重要性」の箇条書き2つ目
- 現状: 「AIが生成するコンテンツとユーザーの意図を正確に結びつけ、クリックへと繋げることで、ターゲットユーザーへのリーチとエンゲージメントを最大化します。」
- 修正案: 「AIが生成するコンテンツとユーザーの意図を正確に結びつけ、クリックへと繋げることで、ターゲットユーザーへのリーチとエンゲージメントを最大化します。」(変更なし、ですが「ターゲットユーザーへのリーチとエンゲージメントを向上させます。」など、少し柔らかい表現も考えられます)
- 理由: 悪くない表現ですが、念のため。
- 「AICTRの対策方法」の箇条書き3つ目
- 現状: 「AICTR対策では、ユーザーがAIを通じてどのような情報を求めているかを深く理解し、それに対応するコンテンツを最適化することが重要です。」
- 修正案: 「AICTR対策では、ユーザーがAIを介してどのような情報を求めているかを深く理解し、それに対応するコンテンツを最適化することが重要です。」
- 理由: 「AIを通じて」も間違いではないですが、「AIを介して」の方が、AIが媒体として機能するニュアンスがより自然に伝わります。
間違いではないが、もっとこうすれば良くなる点(改善提案)
- AIOとAICTRの関係性をより明確に
- 提案: 記事全体でAIOとAICTRの両方に触れていますが、冒頭や「AICTRとは何か?」のセクションで、**「AICTRはAIOの一側面(または具体的な施策の一つ)である」**という関係性を明確に述べると、読者の理解が深まります。AIOがAIシステム全般への最適化という大きな傘であり、AICTRはその中で特にクリック率に焦点を当てた施策であるという位置づけです。
- 例(追記案): 「AIO(AI Optimization)がAIシステム全体への最適化を指す広範な概念であるのに対し、AICTR(AI Click Through Rate)は、その中でも特にAIを介したコンテンツのクリック率を最大化することに焦点を当てた、より具体的な施策や戦略を意味します。」
- 具体例の深掘りまたは追加
- 提案: 「GoogleのSGE」「ChatGPT」「Bing Chat」「Perplexity AI」の名前を挙げていますが、それぞれがどのような形でAICTRに影響を与えるのか、もう少し具体的に解説できると、読者はイメージしやすくなります。
- 例:
- SGE: 「SGEの概要回答で、自社サイトが引用される、あるいは上位に表示されるようなコンテンツ構成が重要」
- ChatGPT/Bing Chat: 「チャットボットが回答を生成する際に、自社サイトの情報を参照し、かつその回答からサイトへの誘導(クリック)を促すような情報の配置や表現」
- Perplexity AI: 「参照元として自社サイトが明記されるため、その参照元がクリックされやすいような信頼性のあるコンテンツ作成」
- 補足: 「AICTRの対策方法」の箇条書きは非常に良いのですが、これらの具体的なサービスに落とし込むことで、より実践的な内容になります。
- 「AI時代のSEO」との関連性強調
- 提案: 記事中でSEOに触れていますが、AIO/AICTRが「SEOの進化形」であるという視点をもっと強調すると、従来のSEO知識を持つ読者にとって、新しい概念への橋渡しになります。
- 例: 「従来のSEOが検索エンジンのランキングアルゴリズムに最適化することであったのに対し、AIOやAICTRは、生成AIやAIアシスタントといった新たな情報提供チャネルにおけるコンテンツの露出とエンゲージメントを最大化することを目指します。」といった導入。
- 網羅性/継続性の示唆
- 提案: AIの進化は速いため、一度対策したら終わりではなく、継続的な検証と改善が必要である旨を追記すると、より現実的で役立つ情報になります。
- 例(結論部分など): 「AIの進化は日進月歩であるため、AICTR対策も一度行ったら終わりではありません。常に最新のAIトレンドやユーザーの行動変化を注視し、コンテンツの最適化を継続的に行っていくことが成功の鍵となります。」
- 箇条書きの表現の一貫性
- 提案: 各見出し下の箇条書きで、「〜です。」で終わるものと、「〜こと。」で終わるものが混在しています。どちらかに統一すると、より読みやすくなります。(例:「〜です。」に統一)
- 例:「AICTRの重要性」の2つ目の箇条書きは「最大化します。」で終わっているので、これに合わせる形です。
これらの提案が、記事のさらなる改善に役立つことを願っています。素晴らしい記事になると思います!
あまりにも変なので、指摘してみました。
「AICTRとは何か?」の見出し下の導入部分
上のような文がありましたが、どのことを言っているのか不明です。場所を確認して教えて。
すると、またトンチンカンな回答が返ってきました。
しかも、AIO対策のドメイン(正しくはaiotaisaku.com)まで間違っていました。
大変失礼いたしました。「AICTRとは何か?」の見出し下の導入部分について、具体的な場所を特定し、ご説明いたします。
ご指摘の箇所は、記事の**目次から数えて3つ目の見出し「AICTRとは何か?」**の直下にあります。
記事の構造として、以下のような順序で記載されています。
- https://www.google.com/search?q=AIOTAIKE.comのヘッダー部分
- 記事タイトル:「AICTRとは?SEOからAIO、AICTRへ。AI時代に必要な概念と対策方法」
- パンくずリスト
- 目次
- 導入部分(「AI時代における情報収集のあり方は、日々進化しています。」から始まる段落)
- 見出し「AIOとは?」
- その説明文
- 見出し「AICTRとは何か?」
- この見出しの直下にある以下の文が、ご指摘の箇所です。
> 「AICTRとは、AIを用いたコンテンツをターゲットとして、クリック率を最大化するための施策や戦略を指します。」 - その後の箇条書き(「AICTRは以下の要素に焦点を当てます。」)
- この見出しの直下にある以下の文が、ご指摘の箇所です。
この箇出し文を、「AICTRとは、AIが生成・利用するコンテンツをターゲットに、クリック率を最大化するための施策や戦略を指します。」と修正することを提案いたしました。
これで場所が明確になりましたでしょうか。
最後は人間のチェックが不可欠
ふだん、いろんなところでお世話になっているAIたちですが、校正がこんなにも出来ないとは思ってもみませんでした。
もちろんAIが完全に校正してくれたら、全部任せられるかと言えば、そうではないと思います。
これは私がよく言っていることなんですが、どんなに高性能なAIも責任を取ることだけはできません。
校正は、単に誤字脱字を発見する作業ではなく、ある意味「責任をとる作業」。そういう意味では、少なくとも校正においては、AIは今後も補助的なツールとして使うのがベストだと思いました。